 食材
食材 塩数の子そのまま食べる?塩抜きしてすぐ食べたいときの時短方法も紹介する
新年の祝いの食べ物として人気の塩数の子は、皆さん新年期間中に楽しまれましたか?塩数の子はおいしいですが、実はちょっとした工夫が必要な食材です。今回は以下の点に焦点を当ててご紹介します。塩数の子はそのまま食べれるのか?塩数の子の塩抜きの仕方
 食材
食材  季節のイベント・行事
季節のイベント・行事 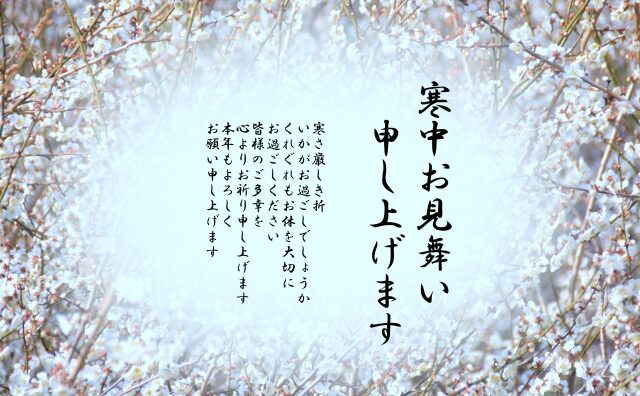 季節のイベント・行事
季節のイベント・行事 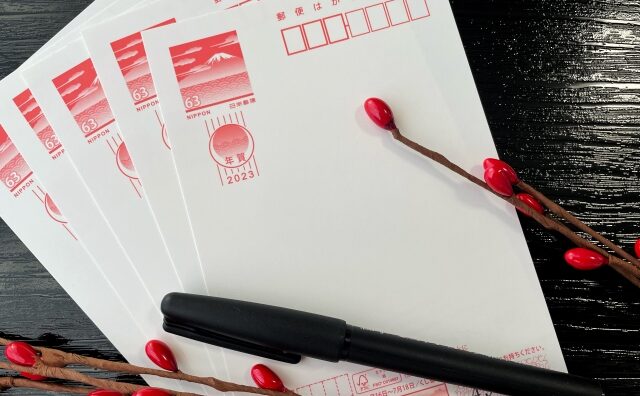 季節のイベント・行事
季節のイベント・行事  季節のイベント・行事
季節のイベント・行事  季節のイベント・行事
季節のイベント・行事  料理
料理  料理
料理